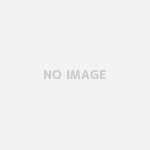今日のテーマは、お米と日本の歴史です。
『お米を知れば、日本の歴史がわかる!』
これは、私の持論です。
なんだか、学校の授業みたいな番組が続いていますね。でも、もう少しお付き合いください。あと二三回くらいかと思います。
本題に入ります。今、日本の歴史への興味が尽きません。府中という歴史のある土地柄や、五月の大國魂神社例大祭くらやみ祭りなども関係してますが、実は、元々、日本の歴史ってなんとなく面倒くさく、大学受験は、世界史で受けました。
家業に戻り、お米の歴史や日本の自然環境との関係をあらためて知ると、ああ、子供のときにこれを知っていれば、日本史の授業がどれだけ理解しやすく、楽しく無理せずに覚えられただろうと思います。
無理せずに、というのは、こういうことです。歴史って、とにかく、丸暗記、年号や人名、できごとを、そっくりそのまま覚えるというイメージですよね。試験はそれでしのげます。でも、あとになって、いったい、その歴史の背景に何があって、どうつながっていったのか、ばらばらに覚えていった、出来事、いくさ、経済、文化などが、どう関連していたのか、わかったようで、わからない、多分そんな感じかと思います。
それが、お米を軸にすえると、一変します。
いくつか紹介します。
まず、稲作が、とにかく生産性の高い穀類という点です。縄文期にも多少の農産物栽培をしていたことをお話しました。しかし、栗や陸稲(おかば)、の栽培では、収量が限られます。それが、水田になると飛躍的に増えます。さらに、お米は毎年作れます。作った田んぼから毎年収穫できます。これも、他穀類と大きく違う点です。すると、人口が増えます。人口が増えれば、もっと水田が作れます。お米は保管ができます。高床式倉庫、習いましたよね。ねずみ返し、覚えてますか?
こうして、大きな集落ができます。人口が増えれば、もっと大きな田んぼを作れます。倍々ゲームですね。
水田を新たに作る、維持をするために、多くの人を動かすことが必要です。リーダシップですね。集落の中に、序列が生まれます。はっきりした組織化です。
さらに、隣にいい田んぼがあれば、欲しくなります。他の集落といさかいが生まれます。集落を守るために、集落の周りに濠(ほり)をめぐらし、高い物見やぐらを建てます。
どこかで聞いた、見たことがありませんか、そんな風景。そうです、佐賀県の吉野ヶ里遺跡ですね。
明らかに身分の違いを示す衣類の痕跡。戦争で傷ついた痕跡が見られる人骨。
こういう歴史の背景が、お米ということです。
二番目に、田んぼを作る技術とその応用です。
まず、田んぼやその周囲を想像してください。山や川から水を引きます。用水路ですね。水路は、今のようなコンクリートではありません。底面と側面の三面は、土を固めたり、石積みです。これも稲作に伴う技術です。
水路に水が流れるためには、ゆるやかなこう配がずっと続くことが必要です。上がったり下がったりでは困ります。しかし、自然の土地はそんなに便利にできてはいません。全体としては、山から海まで下っていきますが、途中は、まさに、山あり谷ありです。それを、土木技術で、きれいにこう配が続く用水路を作っていくのです。
さらに、田んぼは、土を平面にならします。たいらでなければ、張った水が、深すぎたり、浅すぎたり。そこで、平面にならすために、山側を削って、谷側に土盛りします。そうすると、上の田んぼとも、下の田んぼとも、段差が大きくなります。この田んぼごとの高低差を土や石で段々を作り支えます。
さて、これって実は、古墳作りや、城作りと基本同じです。
お城の姿を想像してください。防御のために濠を作ります。水を引いてきます。周りは、土塁や石垣を作ります。弥生時代から営々と気づきあげてきた田んぼを作り維持していく土木技術は、そのまま古墳時代から戦国時代まで生かされています。
今日の最後は、鉄の話です。鉄が国産化されたのは、西暦五世紀頃と言われています。それまで、鉄はほとんどが輸入品でした。鉄が土木や農作業に使えるかどうかは、大変な問題です。木製の鍬や鍬では、大規模な工事はとてもできませんし、農作業もはかどりません。鉄がふんだんに使えるようになると、新しい田んぼを作るスピードが格段に改善しますし、農作業自体が大変楽になります。
そして、鉄は同時に武器でもあります。農業の生産力があれば、人口が増え、たくさんの兵士と鉄製の武器があれば、周囲の集落、国々を従えていくことができます。
古代、最初に鉄の生産が盛んになったのは、吉備、今の岡山です。そして、奈良のヤマト政権も、九州から吉備を通ってきた人が作ったという説もあります。
これが、お米を真ん中に置いてみた日本史の一部です。
次回は、奈良平安鎌倉室町戦国時代を一気にお米視点で語ってみたいと思います。
今日はここまです。
皆さん、お米について知りたい聞きたいことがあれば、何でも結構です。是非、ラジオフチューズまでメールをお寄せください。